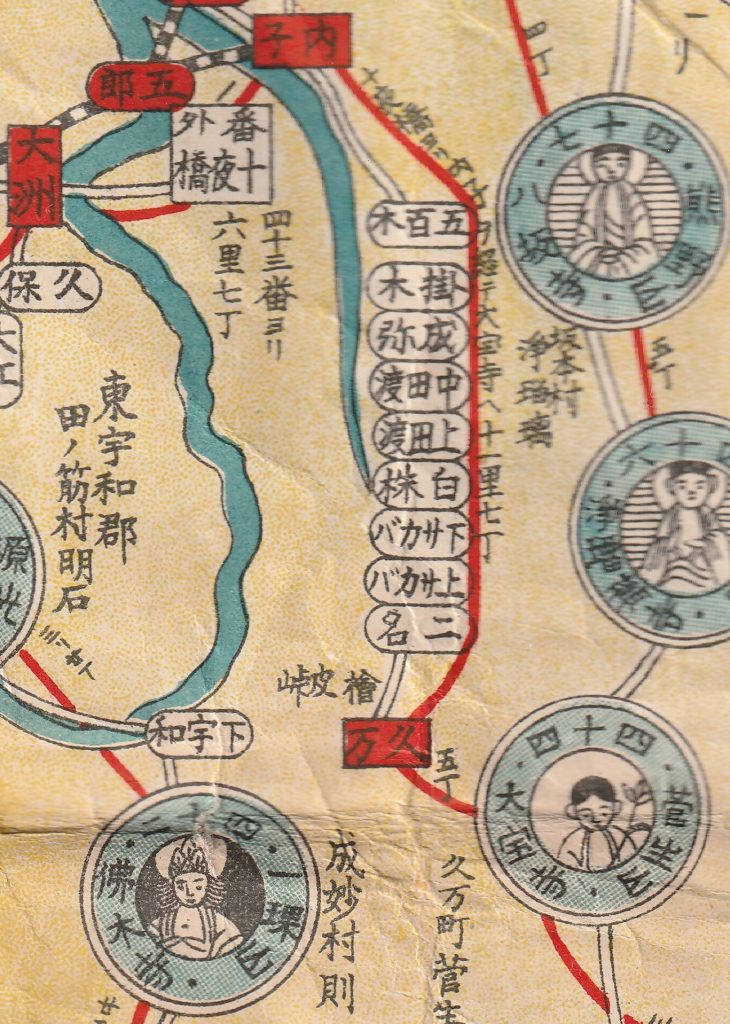10月2日(木)に出前授業「戦時下のくらし」を行った内子町立内子小学校から、学習発表会のご案内をいただき、11月14日(金)にお伺いしました。
6年生のタイトルは「Orizuruに願いをこめて」。まず、23歳で戦死した特攻隊員佐藤新平さんの遺書が児童の皆さんによって読み上げられた後、修学旅行で大刀洗平和記念館を訪れたこと、当館の出前授業を受けたことが述べられました。そして、グループごとに設定したテーマについて調べ学習の成果を発表しました。切符制度、配給制度、代用食、松山空襲、宇和島空襲、特攻隊、表現の自由が奪われたこと、教育を受ける権利が奪われたこと、戦時中の子どもたち、戦時中の学校生活、原子爆弾、戦後も続く苦しみ、今も続く戦争など幅広いテーマが取り上げられました。
出前授業では、戦時中の子どもたち(おもちゃ、通知表)、切符制度、配給制度、代用品、愛媛県下の空襲、原子爆弾と愛媛の関係(パンプキン)について、資料を交えながら紹介しましたが、それらも発表内容に含まれており嬉しく感じました。しかし、嬉しさ以上に感じたのは出前授業では伝えきれなかった点を、児童の皆さんが幅広い視点で深く調査していることでした。特攻隊で戦死した人数、空襲の被害者数などデータ的なことはもちろん、戦時下において表現の自由が奪われたこと、教育を受ける権利が奪われたこと、戦後も続く苦しみ(PTSD、アルコール依存症、家族への影響)など、教科書では触れられないようなことも調査し、ウクライナ戦争についてもウクライナとロシアの双方の立場から捉えていました。6年生としては非常にハイレベルな内容でした。
最後に平和学習の合唱曲「Orizuru」が6年生全員で歌われました。各グループの発表成果を聞いた後だけに、平和への願いが一層深く心に響きました。児童のみなさんの歌声を聞きながら、すでに私たちが「戦争体験者から話を聞く側」から「聞いた話を次の世代に伝える側」になりつつあることも認識しました。今回、学習発表会に参加させていただき出前授業が教育現場のニーズにあったものとなるよう改善と工夫を重ねていきたいと思います。内子小学校の皆さん、ありがとうございました。