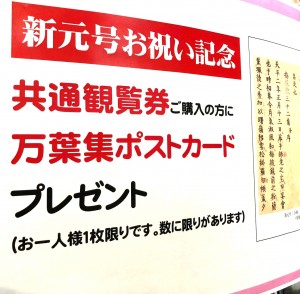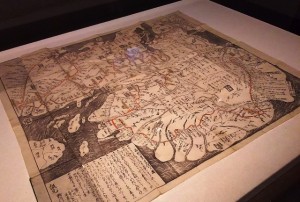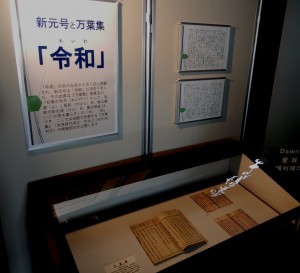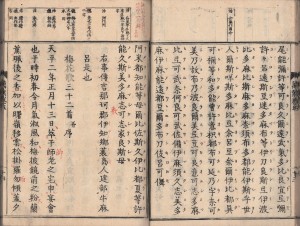9月12日(土)、テーマ展「戦後75年 伝えたい10代の記憶」が開幕しました。本展は、戦時中に10代の多感な時期を生きた若者たちの学校生活・予科練生活・空襲体験を通して、戦争の悲惨さと平和の尊さを考えようと企画しました。
展示では4人の方を取り上げています。日中戦争前後、弓道の授業や勤労作業が取り入れられ、戦時色がしのびよってきた女学生、昭和19(1944)年から通年動員となり、卒業式も動員先の工場で行われた中学生、松山海軍航空隊で2度の空襲に遭い、長野県で特攻要員として訓練中に終戦を迎えた予科練生、昭和20年5月10日、宇和島の初空襲で隣家に爆弾が直撃し、悲惨な光景を目にした小学6年生です。
前半のお2人はこれまでに寄贈いただいた資料の整理を通じて、後半のお2人は聞き取り調査の成果をもとに展示を構成しました。初の試みとして聞き取り調査を展示で放映するとともに、パンフレットも作成しました。日記・日誌・アルバムなどの実物資料に加え、映像やパンフレットもあわせてご覧ください。
戦後75年。本展を通じて10代の置かれていた戦時下の状況をご覧いただくとともに、戦争体験者から直接当時のお話をお伺いする機会が少なくなる中で、今後戦争体験をどのように後世に伝えていくか、あらためて考える機会になれば幸いです。
※テーマ展「伊予市高見Ⅰ遺跡とその時代」と同時開催です。ぜひご来館ください。