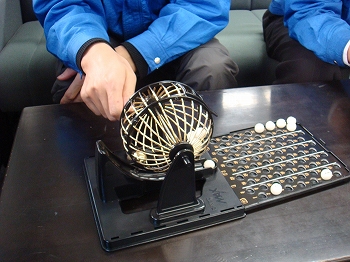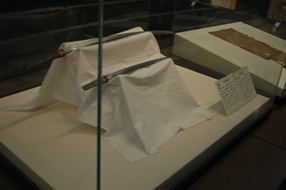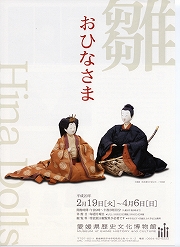肱川河口から約2km上流、JR伊予出石駅の正面には肱川に渡された大和橋、その先には支流大和川沿いに下須戒(しもすがい)の谷筋が伸びます。肱川河口を間近に望むこの川の合流地点の尾根先に、中世に造られたのが大陰(おおかげ)城(下須戒城)です。

大陰城跡麓から肱川河口を望む
戦国末期には矢野氏が城主であったと伝えられますが、この地域の領主に関する当時の確実な資料はほとんどないため、残念ながらはっきりしたことは分かりません。
しかし、大陰城を含む下須戒という地域は、当時の古文書の中にちらほらその名を現します。戦国時代も終盤に近づいた永禄の頃から、道後の河野氏やそれを支援する安芸毛利氏は、喜多郡方面への進出を図ります。その際、喜多郡の中心をなす大洲盆地への主要な進出経路としては、やはり伊予灘沿岸を南下し、肱川をまっすぐ南へさかのぼる方法でしょう。当然、進出する側も守る側も、その通路の入口となる肱川河口は重要な戦略拠点となるわけです。海上交通から河川交通に切り替える場所としても重要であったでしょう。
河野・毛利勢力は進出の足がかりとして下須戒の確保を目指し、また中継拠点として重視していた様子がうかがえます。しかし、安定的確保は難しかったようで、しばしば攻防戦の舞台ともなっています。そうした肱川河口の要衝である下須戒を睨む軍事拠点が大陰城になります。結局、下須戒を含む肱川下流域では、天正13(1585)年の四国平定の時まで河野・毛利勢力を交えた騒乱が続くことになりますが、おそらくその中で下須戒は常に重要拠点とされ、幾多の攻防が繰り返されたと推察されます。
四国平定の後、豊臣政権下に入った伊予では、小早川隆景のもとで城郭の整理が行われますが、実は大陰城はその時の状況がうかがえるという興味深い城の一つです。小早川隆景から家臣乃美宗勝への指示によると、「祖母谷(うばがい)、瀧之城、下須戒、これも一所にまとめたい」としています。この3城はすべて大洲盆地から長浜に抜ける肱川沿いに所在する城で、それぞれに河川交通を押さえる拠点となっていたと推察でき、統一政権下ではその役割を1つの城に担わせようとしたようです。