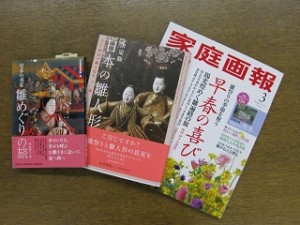毎年恒例の春のイベント、「十二単着付け体験」が近づいてきました。十二単の着付けは3人がかりの大作業です。実際の体験イベントが行われる前に、着付けを行うスタッフが勢揃いして、より美しい十二単の着付けを目指して、段取りをおさらいしています。
最初に着付けの経験があるスタッフが講習しています。初めてのスタッフは一生懸命メモしながら、自分でもできるようにイメージしていきます。
その後、初心者も含めて、メンバーをかえながら、何度も着付けの手順を復習していきます。おひなさまイベントに向けて、特訓の日々が続きます。
なお、十二単は既に応募を締め切っていますが、西条藩松平家のお雛様と同じ袿袴姿に変身できる体験イベントを3月2,3日に実施します。チラシでは13:30~15:30の予定になっていますが、たくさんのボランティアさんのご協力のおかげで、下記のとおり時間を延長して行うことが決定しました。こちらは事前申込は不要ですので、お気軽にご参加ください。
「おひなさまに変身♪」
日 時:3月2日(土)、3日(日)
10:00~12:00 13:00~15:30
対 象:幼児~小学生(身長100~140cm)
参 加 費:無 料