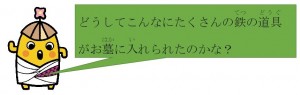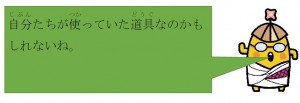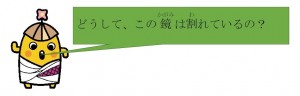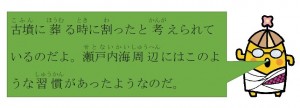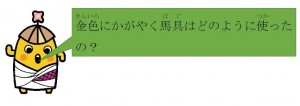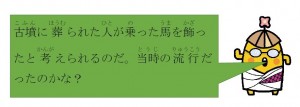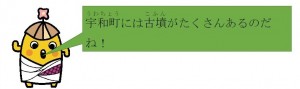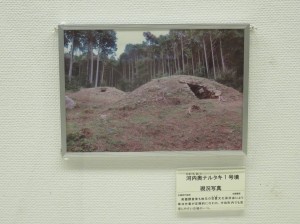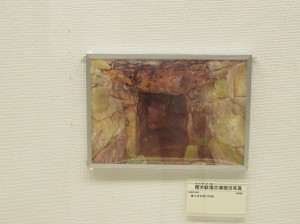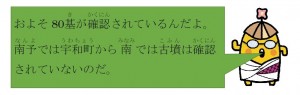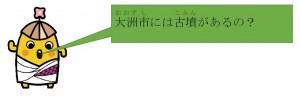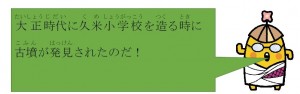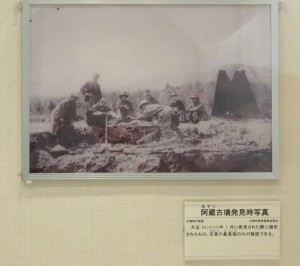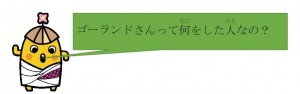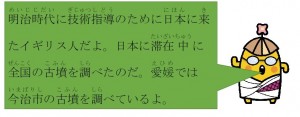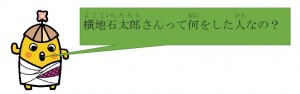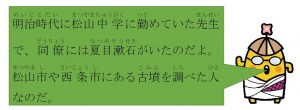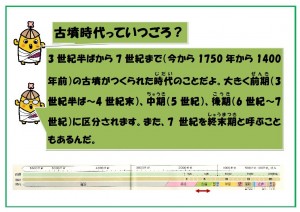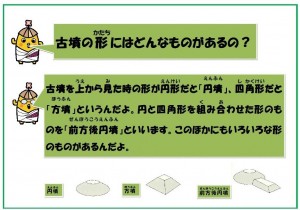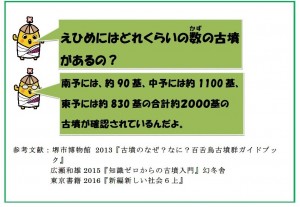『松山市史料集』に「元禄・宝永・正徳・享保年代堀江村記録」という史料が所収されおり、宝永4(1707)年の南海地震による松山付近の被害などが記されているので紹介します。
「十月四日未刻ゟ大地震ゆり出し同申刻迄大地震」とあり、10月4日の未刻(午後2時頃)から申刻(午後4時頃)まで大きな揺れがあったことがわかります。「大地震」が約2時間続いたというのは本震の前後に大きな余震が集中していたことを物語ります。そして史料には発生当日の10月4日から7日までは、一日に8、9回の余震が続き、人々は屋外の仮小屋で過ごし、発生三日後の10月7日から14日までは、一日に3、4回の余震が続き、その後は翌年正月(本震から約2ヶ月後)まで、二、三日に1度は余震があったと書かれています。この史料から、本震発生から数ヶ月間は頻繁に余震を感じていたことになります。これは伝聞情報ではなく、当時の堀江村(現松山市)で感じた揺れであり、当然、伊予国(愛媛県)全体でも同様の状況であったと推察できます。
また、堀江村周辺はじめ松山地方の被害状況についても書かれています。まず安城寺村では瓦葺の長屋が倒壊したものの、それ以外は大きな被害はなかったとあり、堀江周辺では建物の倒壊は少なかったようです。しかし、10月4日の本震によって、「道後之湯之泉留リ申候」とあるように道後温泉の湧出が止まったと記され、松山藩主は地震からの復旧を祈願して、藩領内の七つの寺社、つまり道後八幡宮(伊佐爾波神社)、石手寺、薬師寺、味酒明神(阿沼美神社)、祝谷天神(松山神社)、太山寺、大三嶋明神(大山祇神社)にて祈祷を行わせています。
さて、この史料には津波被害の記述も見られます。ただし松山に襲来した津波ではなく、堀江村から九州方面に出漁していた漁民が経験し、伝聞した情報です。「大地震之時、豊後国佐伯鰯網之日用働ニ堀江村ゟ三拾人余参候処ニ、佐伯ニ而地震止、半刻程過申と常々ゟ汐干申候而其まゝ四海波汐之高サ四拾間余茂みち上リ其引汐ニ佐伯浦之家々沖ヘ不残引取申候、老女子共餘多死申候由、同十四日ニ漸命からがら仕合ニ而当村帰帆仕候」とあり、地震の際、堀江村の漁民30人余が豊後国佐伯領(現在の大分県佐伯市)のイワシ網の日傭稼ぎに出稼中で、佐伯湾外で操業していましたが、地震直後に湾を襲った津波で、佐伯の家々が沖に流され、数多くの死者が出ました。そして堀江村の漁民は地震発生の10日後の14日に、命からがら逃げ帰ったことがわかります。また大坂(現大阪府)では船の被害は815艘に及び、死者は1万2500人余であったと伝わっているとも記され、瀬戸内海各地でも被害が見られ、甘崎城(現今治市上浦町)などが被害を受けたほか、家屋倒壊による死者もいました。史料には、今後は家屋の被害があっても速やかに高所に避難することが教訓として書かれています。
以上、この「堀江村記録」は、宝永南海地震当日の様子のみならず、余震の状況、道後温泉の湧出が止まったこと、大坂、瀬戸内海各地、豊後水道特に佐伯地方での津波被害を伝える貴重な地震史料といえます。