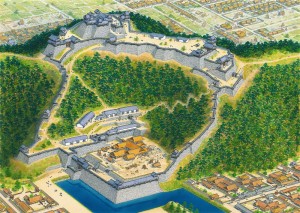みなさん、こんにちは。
博物館の常設展示はいつも同じ展示内容ではなく、少しずつ変更しています。季節に合わせて変えている展示もあります。
先日9月26日に歴史展示室1「原始・古代」の「伊予の律令体制」のコーナーでは一部を展示替えしました。
元々の展示はこのような様子でした。

展示替え後はこちらです。前回と同じ展示資料もありますが、レイアウトやキャプションを大幅に変更しました。

古代の伊予国(愛媛県)で使用されていた文房具の一部をご覧いただけます。
展示のラインナップとしては銅印や硯2種類(円面硯・風字硯)、伊予砥となっています。
その中から伊予砥(久米窪田Ⅱ遺跡出土)について紹介したいと思います。

伊予砥とは伊予で産出された砥石のことで、平安時代中期成立の『延喜式』などにも記述が見られます。古代における特産物の1つであり、税物として中央に運ばれていました。このような伊予砥は刀の刃を研ぐために利用されており、現在でもこの使用方法は残っています。
古代には木簡などに文字が書き記されていました。木簡の使用用途は「文書」と荷物などに付けた「付札」に大きく分かれ、伊予の荷札木簡は藤原京・平城京・長岡京で出土しています。
木簡への書き損じや再利用のために小刀を用いて木の表面を剥ぎ、新しい面に書いていたと考えられており、小刀の刃を研ぐのにも砥石が使われていました。その砥石を持ち運びしやすくしたものが提砥(さげと)であり、砥石には穴が穿たれており、そこに紐を通し、ぶら提げて持ち運んでいたと思われます。
少しずつ変わっていく常設展示室で、以前来館された時との違いを発見しに博物館へ訪れるのもいいのではないでしょうか。
ご来館をお待ちしております。