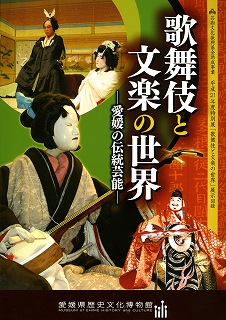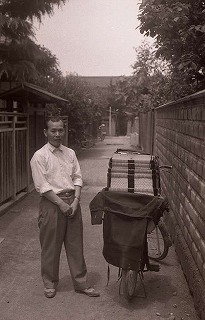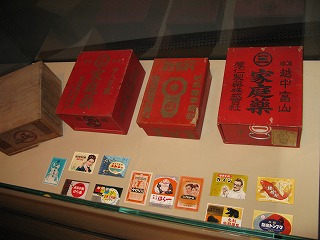エントランスから展示室入口を入ってすぐの中庭に、今年は棉の栽培にチャレンジしています。棉の種はれきはく友の会の会員さんに分けていただきました。
5月初めに植えた棉は、ムシに食べられて全滅し、もう一度種をまきなおしたり、雨が少なくて成長が遅かったりと気をもみましたが、やっと昨日、花が咲きました。

分けていただいた綿の種は、花の色からみると和綿ではなく洋綿のようです。

中庭は建物に囲まれているせいか風が強く吹いて棉が倒れてしまうので、ボランティアさんたちにもご協力いただいて支柱を立てました。棉が無事収穫できるとよいのですが・・。
愛媛県内における棉の栽培について調べてみると、松山・今治・西条付近で多く栽培され、明治以降も水の不足する地域を中心に盛んに栽培が行われていたようですが、アメリカ綿の輸入増加に押されて明治27年頃から急速に衰退してしまいました。
展示室へ向かう年配のお客さまの中には、中庭の棉にお気づきになって懐かしく感じられる方がいらっしゃるようです。