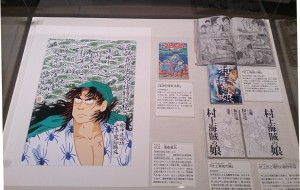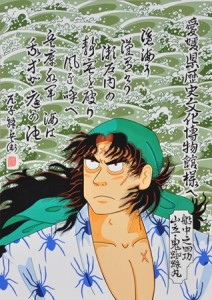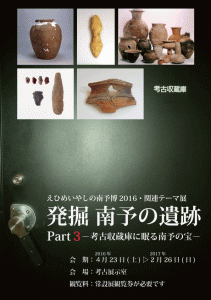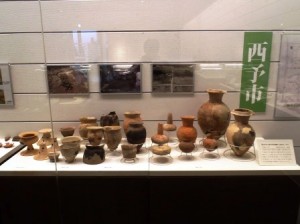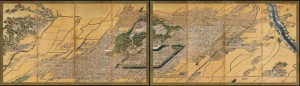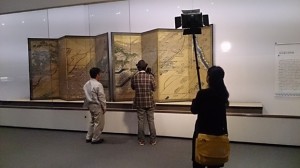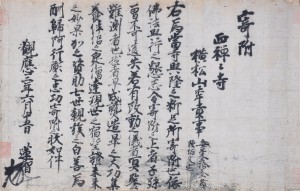先日、民俗展示室「愛媛のくらし」の展示資料を一部展示替えしました。
蚊帳…夏の夜、涼しく安眠するために大事なことは蚊を防ぐこと。海の家では布団を敷いて蚊帳を吊っています。
回転式除草機…夏は、稲がよく育ちます。しかし雑草もすぐ伸びます。農家では、草刈り・草取りが大事な仕事でした。かつての除草作業は、這うように田んぼの中を進まなければならず、とても大変でした。
里の家の前にあるのは回転式除草機。田植えが正(せい)条(じょう)植え(同じ間隔で苗を受ける方法)で行われるようになると、除草機を使って、立ったままで除草ができるようになりました。
桑摘み爪…夏は、田んぼの仕事の他に、養蚕も行う地域が多くありました。山のくらしのモデルとなった西予市城川町野井川竜泉地区も、その一つです。
蚕がよく育つためには、食料となる新鮮な桑の葉が欠かせません。桑の葉を摘むための、専用の道具もありました。
海、山、里…それぞれの地域では、その地形や気候に応じたくらしが営まれていました。しかし、共通する仕事が全くなかった訳ではありません。その一つが養蚕です。
愛媛での養蚕は明治期以降に急速に広まり、海辺、山あい、里…県内の広い地域で、人々は「お蚕さん」を育てていました。今回は、養蚕で使われた道具も展示しています。