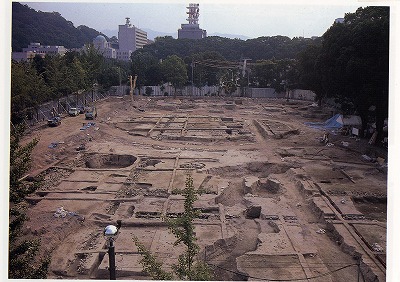県民館跡地出土華南三彩壺片(愛媛県教育委員会蔵)
これは、壺の底部に近い部分の破片です。緑色、茶色、黄色の釉薬が掛けられた、大変カラフルなやきものです。中国の南部地方で16世紀末から17世紀代に焼成されたと考えられています。
このようなやきものは、中世末から日本に輸入されていました。茶道具や座敷飾りなどとして使用されたと考えられます。大友氏の府内城下町でも出土事例があり、国内の寺院にも完形の伝世品の壺が数例あります。松山城三之丸でも破片が見つかっていることから、松山藩の武士たちも所有していたことがわかります。当時の人々にとって、新鮮な色彩だったのではないのでしょうか?
破片になってしまっているので形や大きさが想像できませんので、展示室では当館所蔵の華南三彩五耳壺を一緒に展示しています。あわせてご覧ください。